キャンペーンを活用して無料で稼ぐ
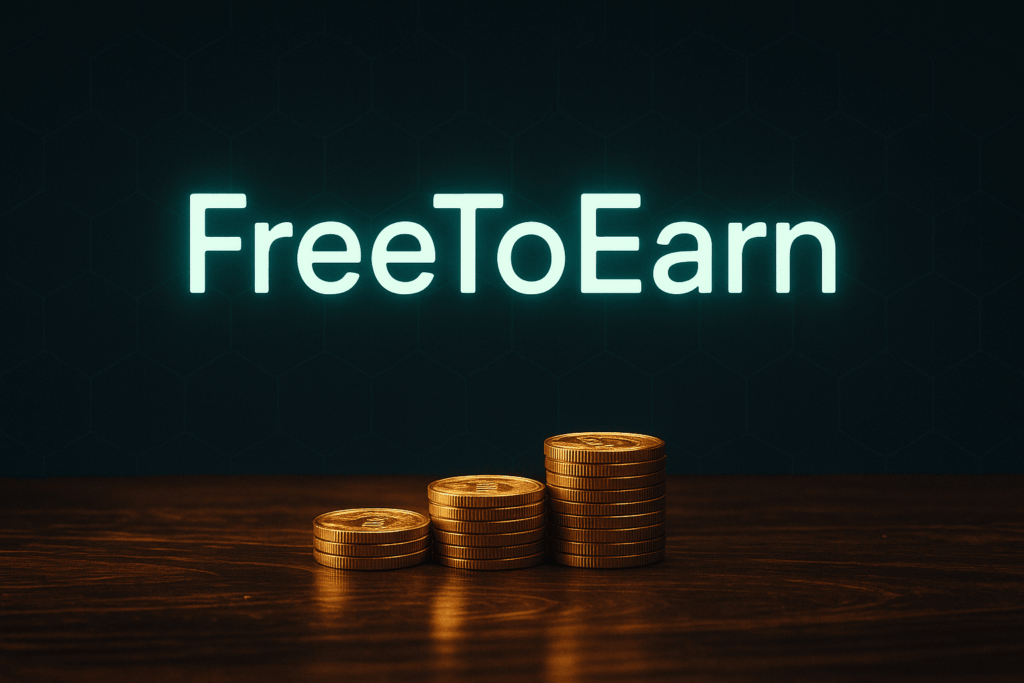
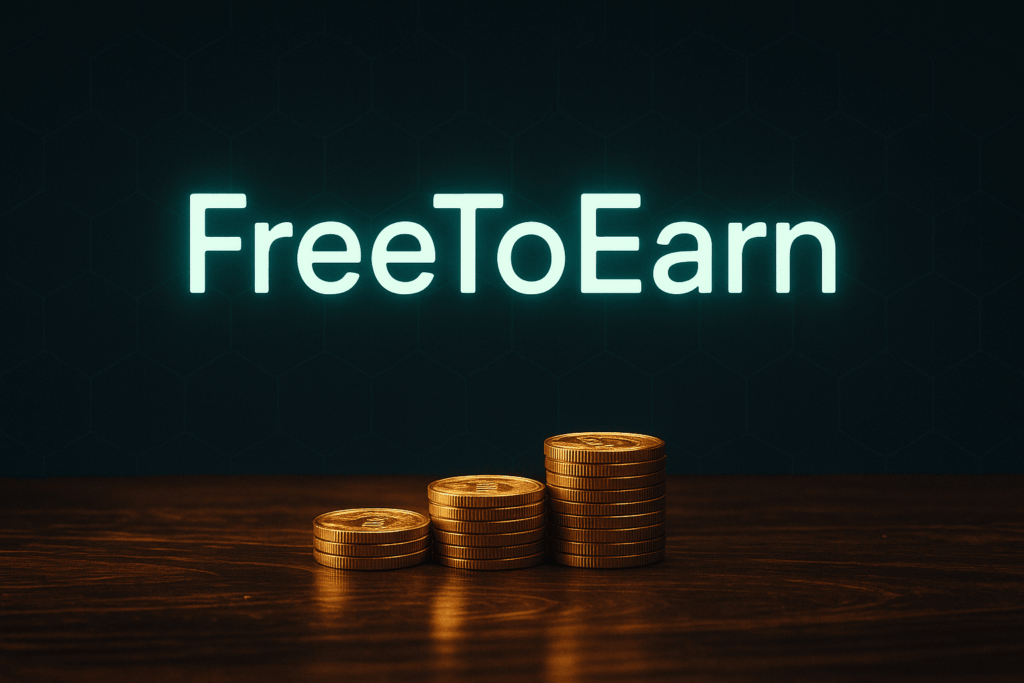
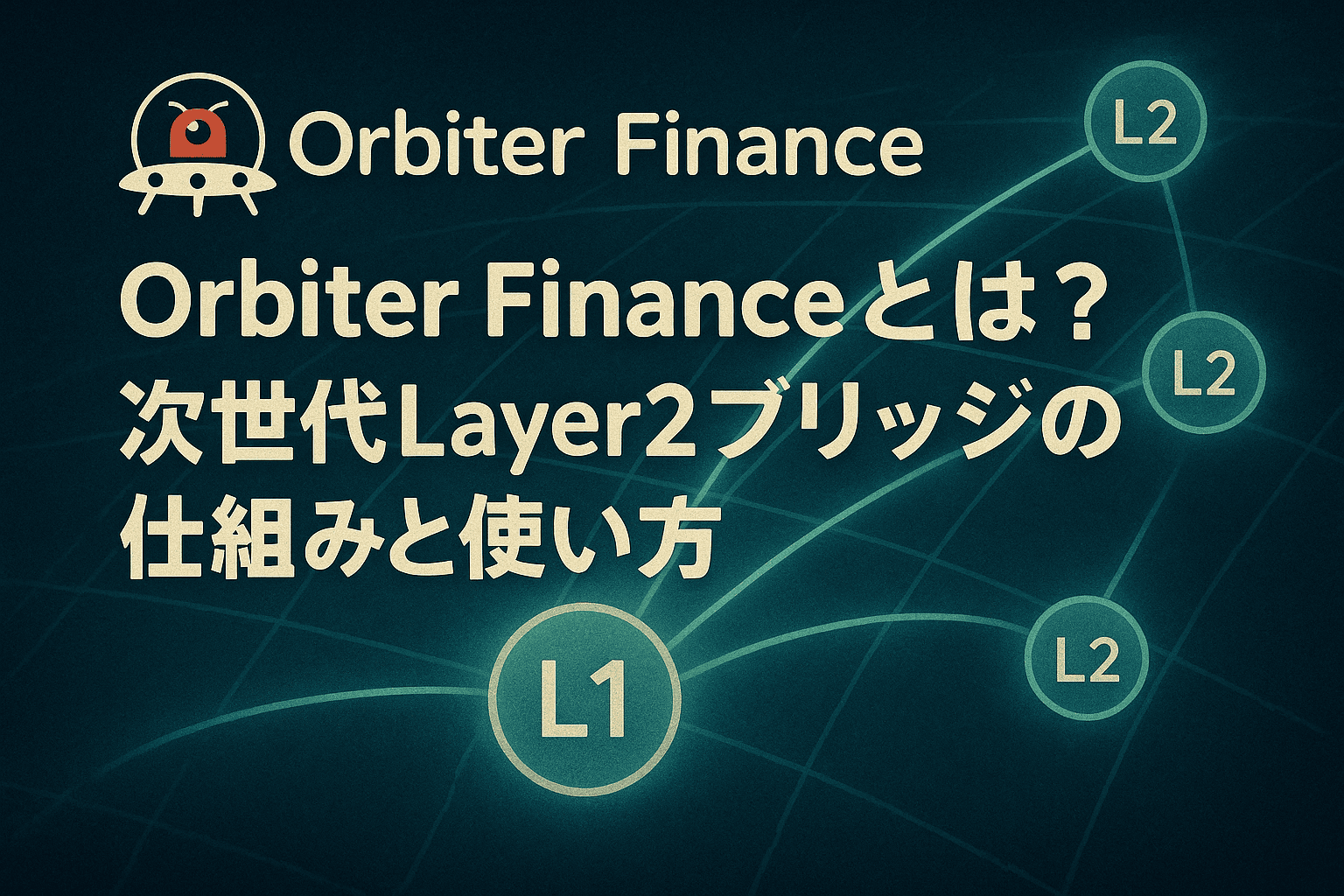
Orbiter Financeは、イーサリアムのメインネット(L1)と複数のレイヤー2(L2)ネットワーク間で資産をブリッジするための分散型クロスロールアップブリッジです。
従来のブリッジのようなラップド資産のミントやバーンを必要とせず、独自の“楽観的”メカニズムによって高速かつ低コストでの資金移動を可能にしています。2021年のサービス開始以来ユーザー数を着実に増やし、累計で430万以上のユーザーに利用され約280億ドル相当の資産移動を達成、現在も成長を続けています。
2025年には独自トークン「OBT」をローンチし、初期ユーザーへのエアドロップを実施するなど、一層の分散化とコミュニティ活性化に踏み出しました。この記事ではOrbiter Financeの要点をまとめ、その特徴や使い方、安全性、トークン情報までを詳しく解説します。




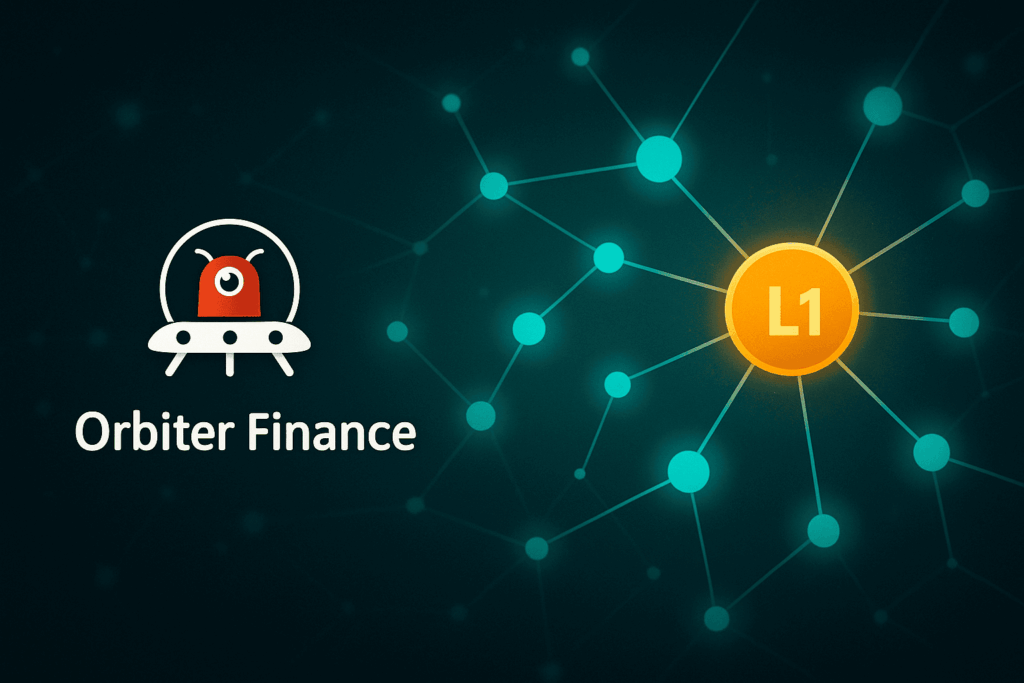
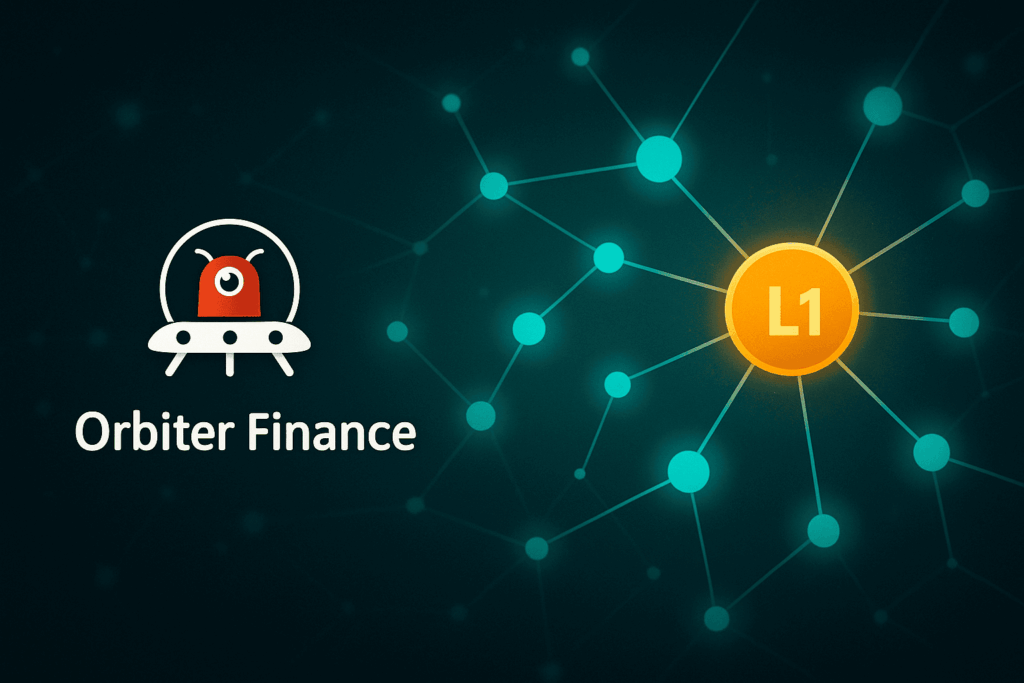
Orbiter Finance(オービターファイナンス)は、Ethereumエコシステム内の異なるチェーン間(L1⇔L2やL2同士)の資産移動を可能にするブリッジプロトコルです。特に複数のレイヤー2(Rollup)間の橋渡しに特化しており、ユーザーがETHやUSDC/USDTなどのイーサリアムネイティブ資産を様々なネットワーク間でシームレスに送金できるよう設計されています。Orbiter Financeを利用すれば、イーサリアムの高額なガス代や時間のかかる処理を回避し、ほぼ即時かつ格安のクロスチェーン転送が実現できるとされています。
他のブリッジとの大きな違いは、中央管理のコントラクトに資産を預けない点です。Orbiterでは従来見られるようなラップトークンの発行を行わず、資産そのものを直接別チェーンへ移す形態を取っています。このため送金元・送金先の両チェーンで常にネイティブ資産として扱われ、ユーザーは複雑な操作なしに資産を移動できます。
実際、対応ネットワークも年々拡大しており、Arbitrum・Optimism・zkSync・Polygonといった主要L2はもちろん、Solanaなどの他エコシステムや新興のZKロールアップにもいち早く対応しています。2024年時点で対応チェーンは70以上にのぼり、Ethereum圏外では早くもBitcoinのレイヤー2ソリューション(例えばLightningの互換チェーンであるB² Networkなど)にも接続する積極性を示しています。こうした幅広い互換性と将来性から、Orbiter Financeはマルチチェーン時代の「縁の下の力持ち」として注目を集めています。
Orbiterのブリッジ動作は、ユニークな「楽観的クロスロールアップ取引」の仕組みによって支えられています 。ユーザー(Sender)はまず送金元チェーン上で指定されたアドレスに資産を送付します。この受取アドレスはブリッジ役となるMaker(メーカー)と呼ばれる流動性提供者のEOA(外部所有アカウント)です。つまりユーザーはスマートコントラクトではなく普通のウォレット宛てに送金する形となり、ここが他のブリッジとの大きな違いです 。ユーザーから資産を受け取ったMakerは、対応する額(手数料控除後)を送金先チェーン上でユーザーのアドレスに送金します。これによりブリッジ処理が完了し、ユーザーは短時間で別チェーン上に資産を移せるという流れです。
このように、Orbiter Financeでは送金元でコントラクトを呼び出す必要がありません。そのため通常のL1-L2ブリッジよりトランザクションのガス消費が圧倒的に少なく、ETHブリッジ時のガス使用量は約21,000に抑えられています(通常のブリッジでは120,000〜450,000ガス程度) 。加えてZK(ゼロ知識)技術による工夫や処理の簡素化によってブリッジ完了までの時間は平均10〜20秒程度と非常に高速で、他のブリッジに比べ大きな優位性となっています 。
一方、「第三者(Maker)を信用して資産を移す」という仕組み上、安全性が気になる方もいるでしょう。Orbiterではこれを担保するためにオプティミスティック(楽観的)な前提+アービトレーション(紛争処理)機構を導入しています 。全ての取引は基本的に正しく行われる前提で即座に処理されますが、万一不正やミスがあればユーザーは異議を申し立てることができます。Makerはあらかじめプラットフォーム側に証拠金をデポジット(預託)しており、不正が確認されればペナルティとしてその保証金が没収され被害ユーザーに補填される仕組みです。またOrbiterはZK-SPVと呼ばれる暗号学的証明技術も採用しており、チェーン間転送の正当性を数式レベルで検証しています。この二段構えのアプローチにより、中央管理者がいなくても高い安全性が保たれているのです。
実際、2021年のサービス開始以降Orbiterで重大なセキュリティ事故は一件も報告されていません。開発チームは独自のスマートコントラクト基盤(O⚊Poolと呼ばれる流動性管理プール)と分散型のメーカーネットワークを組み合わせ、**「効率と安全の両立」**を実現しています。ブロックチェーン業界ではクロスチェーンブリッジのハッキング被害が相次いできただけに、Orbiter Financeの無事故記録と徹底したセキュリティ設計は大きな安心材料と言えるでしょう。
Orbiterでは送金が片道10〜20秒程度で完了します 。ZK技術による即時検証と、シンプルなEOA間送金の組み合わせにより、ブロック承認待ちの時間を最小限に抑えているためです。他のブリッジのように数分〜数十分待たされるストレスがなく、ストレスフリーに資産移動できます。
スマートコントラクトを極力呼ばない設計のため、トランザクション手数料(ガス代)が非常に安価です 。実際の手数料は送金額の数パーセント未満+わずかな固定分となっており、例えば「1 ETHをメインネットからzkSyncへ送る場合、合計約0.0017 ETH(約0.17%)の手数料」で済みます。この水準は他のブリッジや公式ブリッジより割安なケースが多く、特に小口送金では恩恵が大きいです(※市場状況や経路によっては他サービスより高くなる場合もあります )。
前述の通り、Orbiterはサービス開始以来ハッキング等のセキュリティ事故ゼロを継続中です。独自の仲裁システムやZKによる検証技術で、不正な送金を未然に防ぎます。また主要なスマートコントラクト部分については監査も実施済みであり、コミュニティ主導の厳格なテストも行われています。こうした多層的なセーフティネットにより、「ブリッジ=危険」という従来のイメージを覆す安全性を確保しています。
Orbiterは最初期からイーサリアムL2間ブリッジに注力し、現在では70以上ものチェーンを接続しています。Arbitrum・Optimism・Polygon・zkSyncといったメジャーL2はもちろん、新興のZKロールアップ(LineaやStarkNetなど)や他チェーン(Solana、BSC、Avalanche等)への拡張も積極的です。特にEthereumのL2領域では最新技術への追随が早く、例えばPolygon zkEVMやScroll、Baseなどの新ネットワークにもいち早く対応しています。さらにEthereum外ではBitcoinのLayer2(例:BitDAOのLayer2「B\u00b2 Network」)やSolanaにも接続を拡大しており、マルチチェーン統合の先頭を走っています。ユーザーにとっては「Orbiterさえあれば主要どころはほぼカバーできる」心強い状況になっています。
Orbiter Financeは現在まで開発チーム主導で運営されてきましたが、今後はさらに分散化が進む予定です。実際、Makerノード機能の一般開放が計画されており、ユーザーが自ら流動性提供者(Maker)として参加し手数料収入を得られるようになる見込みです。2022年時点ではMaker機能は開発中でしたが、既にOrbiterチーム自身が十分な流動性を提供しているためブリッジ運用には支障がありません。加えて2025年には独自トークン(OBT)を発行し、コミュニティへの大規模エアドロップを実施しました。このOBTはガバナンストークン兼ステーキング報酬の役割を担い、今後Orbiterの運営意思決定にコミュニティが参加していくための鍵となります。活発なDiscordやGuildでのランク制度(Orbiter利用回数に応じた称号NFTなど)もあり、ユーザー主導でプロジェクトを盛り上げていく土壌が整えられています。
実際にOrbiter Financeを使って異なるチェーンへ資産をブリッジする流れを、基本的な手順に沿って見てみましょう。操作にはWeb3対応ウォレット(MetaMask等)が必要です。
Orbiterでブリッジ可能な資産はETH、USDC、USDTです。まずブリッジ元のチェーン上で、送りたい資産を必要な額だけ用意します(例:Arbitrum上でETHを0.1 ETH用意)。ガス代も考慮し、少し余裕を持った残高を確保しておきましょう。
ウォレットの準備ができたら、WebブラウザでOrbiter Financeの公式サイト【21†orbiter.finance】にアクセスします。ページ右上の「Connect Wallet(ウォレット接続)」をクリックし、MetaMask等のウォレットをサイトに接続しましょう。接続要求を承認すると、サイト上でウォレットが認識されブリッジ操作の準備が整います。
サイト上のUIで、まず送金元(From)チェーンと送金先(To)チェーンを選択します。次にブリッジする資産の種類(ETH/USDC/USDT)と金額を入力します。例えば「From: Arbitrum、To: Optimism、Asset: ETH、Amount: 0.1」のように指定します。入力すると、推定手数料や受取見込み額が画面に表示されます。内容を確認し問題なければ「Send」ボタンをクリックしましょう。
「Send」を押すとウォレットが立ち上がり、送金トランザクションの確認画面が表示されます。手数料(ガス代)や送金額に間違いがないか最終確認し、「Confirm and Send」で承認します。これで送金元チェーン上で指定アドレス(Maker宛て)への送金が実行されます。Orbiterのサイト上では進行中のブリッジ状況を確認でき、数秒待つと「ブリッジ完了」の表示とともにトランザクションIDが記録されます 。
送金先チェーン上の自分のウォレットアドレスに、指定した資産が届いているか確認します。例えばArbitrum→Optimismへ0.1 ETH送った場合、Optimism側のウォレット残高に約0.1 ETH(手数料差引後の額)が増えているはずです。Orbiterは非常に転送が速いため、ほとんど待たずに着金確認できるでしょう。履歴タブからは過去のブリッジ履歴(日時・資産・ネットワーク)も確認できます。
rbiter Financeの独自トークン(OBT)は、コミュニティガバナンスとステーキング報酬を目的として2025年に導入されました。総発行量は100億枚で、Ethereumメインネットおよび主要なL2(ArbitrumやBaseなど)上で展開されています。このトークンはOrbiterプラットフォーム上での手数料割引や投票権などに利用される予定で、プロジェクトの更なる分散化の鍵となる存在です。
特筆すべきは、OBTリリースに伴い行われた大規模エアドロップ(無料配布)キャンペーンです。Orbiterチームは初期ユーザーや貢献者に報いるべく、トークン総供給量の最大40%をコミュニティへ配布する計画を発表しました(初回エアドロップでは22%相当を割当)。エアドロップ対象となったのは、2021年12月から2023年にかけてOrbiterを少なくとも2ヶ月以上利用したユーザーや、Orbiter関連のNFT(エースパイロットNFT等)を保有するユーザー、そしてプラットフォーム上で40ポイント以上を獲得したユーザーなどです。これらの条件を満たすアクティブユーザーに対し、スナップショット(対象者抽出)が行われ、OBTの無料配布権利が付与されました。
初回のエアドロップは2025年1月20日にトークンローンチと同時に開始され、同年1月16日時点のスナップショットに基づき対象者が決定されました。配布は複数回のフェーズに分けて行われ、1月20日から順次Claim(請求)受付が実施されています。実際に対象ユーザーはOrbiter公式サイトのエアドロップページでウォレットを接続し、受取可能なOBT残高を確認して請求する形となりました。その後もコミュニティ向けエアドロップは段階的に継続されており、**2025年7月には第5回目のアンロック期間(7月10日〜13日)**が設定されるなど、ロイヤルユーザーへの配布が続いています。OBTは現在、KuCoinやGate.io、Bitgetといった取引所にも上場し流通が開始されており、エアドロップで受け取ったトークンを売買・活用することも可能です。
エアドロップへの参加方法としては、Orbiterを積極的に利用してO-Points(オーポイント)を貯めることが有効でした。Orbiter公式サイトでは各種タスク(ブリッジ利用やSNSフォロー等)をこなすことでポイントが貯まり、一定以上のポイント獲得者がエアドロ対象となる仕組みが採用されました。今後も追加のエアドロップや報酬キャンペーンが行われる可能性があるため、Orbiterコミュニティに参加し最新情報をチェックするとともに、日頃からプラットフォームを活用しておくと恩恵を受けられるかもしれません。
Ethereumのレイヤー2時代において、Orbiter Financeはチェーン間の壁を取り払う重要なインフラとして躍進しています。独自の楽観的ブリッジ機構とZKテクノロジーにより、高速・低コスト・高セキュリティという難題をクリアし 、数百万規模のユーザーに支持されるまでに成長しました。ArbitrumやOptimismを始めとする多数のネットワークをシームレスに繋ぐその姿は、まさに**「マルチチェーン時代の架け橋」**と言えるでしょう。
もっとも、クロスチェーンブリッジ利用時の基本的な注意点(小額テスト送金の推奨、秘密鍵管理の徹底など)はOrbiterでも同様です。幸いOrbiterは直感的なUIで初心者にも扱いやすく設計されていますが、資金移動の際は常に慎重さを忘れず、送金先ネットワークやアドレスの誤りがないか確認する習慣が大切です。
今後、Orbiter Financeは独自トークンOBTを軸にコミュニティ主導のプロジェクトへと進化していくでしょう。ユーザー自身がネットワーク運営に参加できる時代も目前です。レイヤー2の普及とともにクロスチェーン需要はますます高まると予想され、Orbiterのような信頼性の高いブリッジの価値は一層増していくはずです。マルチチェーン環境で資産を自由に行き来させたい中級者以上のユーザーは、ぜひOrbiter Financeを活用してその利便性を実感してみてください。