キャンペーンを活用して無料で稼ぐ
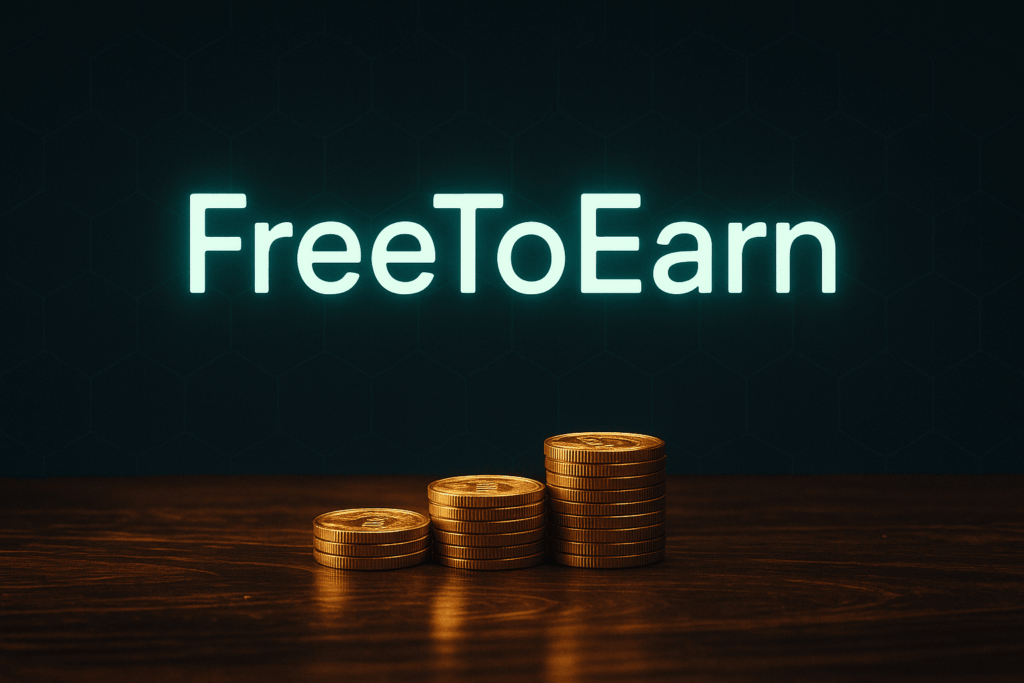
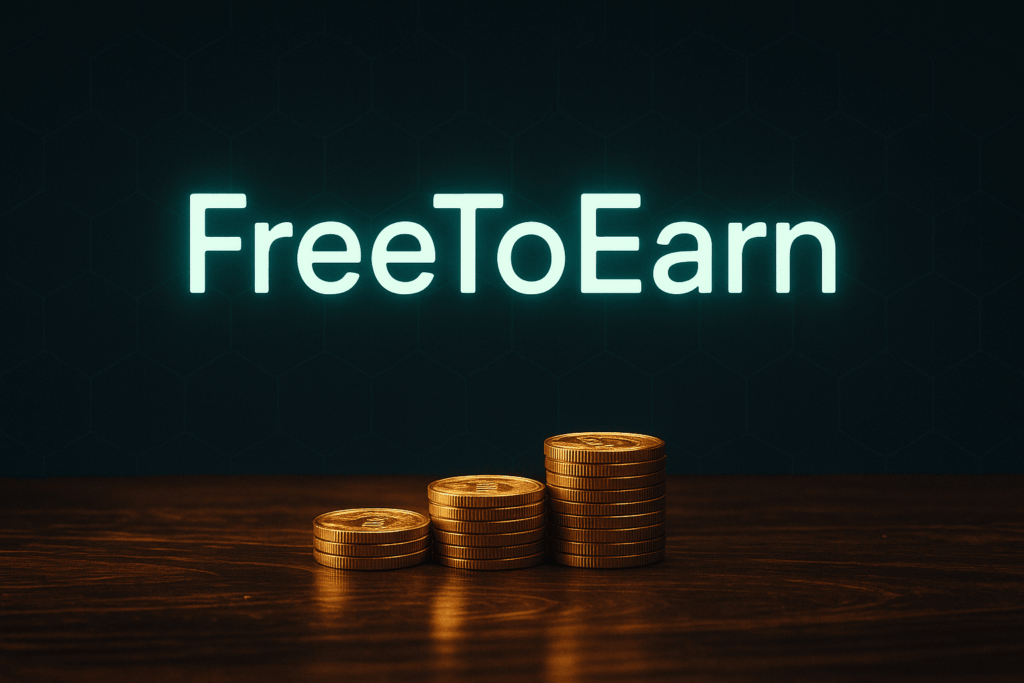

JPYC(ジェイピーワイシー)は、日本円と価値が連動する注目のステーブルコインです。
2025年秋にも国内初の円建てステーブルコインとして正式に発行が開始される見通しであり、仮想通貨ユーザーだけでなく一般の方からも大きな関心を集めています。
「JPYCはいつ買えるの?」
「どこでどうやって購入するの?」
「手数料はかかるの?」
といった疑問にお答えするため、本記事では最新情報をもとにJPYCの発売予定日、具体的な買い方、手数料や特徴について丁寧に解説します。
未確定部分は予想しつつ、確定次第随時更新予定。




JPYC(JPYコイン)とは、JPYC株式会社によって発行される日本円と価値が連動したステーブルコインです。1JPYCが常に1円の価値になるよう設計・運用されており、価格変動の激しいビットコインなどの一般的な暗号資産とは異なり、日本円と同等の価値がデジタル上で保たれる点が特徴です 。言い換えれば、ブロックチェーン上で円をそのまま使っているような感覚で利用できるデジタル通貨です。
JPYCは従来の日本の法律上、暗号資産(仮想通貨)ではなく「前払式支払手段」に分類されてきました。実際、2021年のサービス開始当初は「JPYC Prepaid(プリペイド型JPYC)」として提供され、プリペイドカードや電子マネーのようにチャージして使う形式を取っていました。これは当時、ステーブルコインに関する法整備が整っていなかったための暫定的な措置でした。しかし2023年の資金決済法改正によってステーブルコインが「電子決済手段」として正式に位置付けられたことを受け、JPYCは本格的なステーブルコインとして新たに発行される計画が進められています 。
※2025年5月30日をもって旧「JPYC Prepaid」の新規発行は終了しています。既存のトークンは引き続き利用可能ですが、今後は新しいJPYC(電子決済手段としてのステーブルコイン)に移行予定です 。
なお、JPYCはイーサリアムやポリゴン、アスターなど複数のブロックチェーン上で発行・流通します 。これにより、多様な環境でJPYCを利用でき、ユーザーは自分の用途に合わせて最適なチェーン(ネットワーク)を選択可能です。各チェーンによって取引手数料(ガス代)や処理速度が異なるため、自身の目的に応じて選ぶことで手数料を抑えたり高速に送金したりといったメリットを享受できます。
【日経特報】国内初の円建てステーブルコイン、金融庁承認へ JPYCが秋にも発行https://t.co/IuJfott5py
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) August 17, 2025
JPYCは2025年秋頃に一般向け販売が開始される見込みです。
具体的には、金融庁が8月中にもJPYC株式会社を資金移動業者(第二種資金移動業)として登録し、その数週間後にはJPYCの販売が開始される予定だと報じられました 。この報道に対し、JPYC社の岡部典孝代表も「金融庁承認へとの記事は事実」と認めており、できるだけ早く発行を開始すべく準備を進めているとコメントしています(※X〈旧Twitter〉上の発言より)。つまり早ければ2025年9月中にもJPYCを購入できるようになる可能性が高まっています。
販売開始時期が注目される背景には、JPYCが日本で初めて正式に承認される円建てステーブルコインである点があります 。2023年の法改正後も円に連動するステーブルコインの発行事例はなく、JPYCが初のケースとなる見通しです。これが実現すれば、日本円ベースで価値を安定させたデジタル通貨が一般に利用できる新時代の幕開けとなります。JPYC社は今後3年間で累計1兆円規模のJPYC発行を目標に掲げており、日本国内外での送金・決済、DeFi(分散型金融)など幅広い用途での活用を見据えています 。
現時点(2025年8月)でJPYCをすぐに購入することはできません。 前述の通り旧JPYC(JPYC Prepaid)の新規販売は停止されており、新しいJPYCの発行開始を待つ必要があります。ただし、販売開始に備えて事前に準備できることもあります。
JPYCは発売開始後、主に2つの方法で入手できると考えられます。一つはJPYC公式サイトから直接購入する方法、もう一つは暗号資産取引所で取引する方法です。それぞれの手順や特徴を詳しく見てみましょう。
JPYCの基本的な購入方法は、公式提供の「JPYC販売所」を利用する方法です。
具体的には、JPYC公式サイト上で購入申し込みを行い、自分名義の銀行口座から指定口座へ日本円を振り込むと、その金額相当のJPYCが自分のデジタルウォレットに送付されます 。発売開始後はまずこのルートでJPYCを手に入れる形になるでしょう。
公式販売所を利用するメリットは、発行元から直接1JPYC=1円のレートで購入できるためレートが常に安定していることです。初回利用時にはJPYC社での本人確認(KYC)が必要となる見込みですが、一度登録すれば銀行振込だけで簡単に円をJPYCに交換できます。
受け取りにはEthereumやPolygon対応の暗号資産ウォレット(例:MetaMask等)を自分で用意し、購入申請時にウォレットアドレスを指定します。発行開始当初はWeb上で円をJPYCに替える新鮮な体験となるため、公式から発表される購入手順の詳細をよく確認して進めましょう。


JPYCが発行開始された後、国内の主要な暗号資産取引所で取り扱われる可能性があります。例えばコインチェック(Coincheck)は国内大手の取引所であり、新規ユーザーでも口座開設が簡単なことから初心者に人気です。
現時点ではコインチェックでJPYCを直接購入することはできませんが、仮想通貨取引に興味を持った方は今のうちに信頼できる取引所で口座を作っておくことをおすすめします。
コインチェックなら500円程度からビットコイン等の購入も始められるため、JPYC発売までに取引の感覚を掴んでおくのも良いでしょう。


JPYCを購入・利用する上で、手数料がどの程度かかるのかは気になるポイントです。
結論から言えば、JPYCの発行(購入)や償還(円への引き戻し)にかかる手数料は基本的に無料です
発行元であるJPYC株式会社は、JPYCの発行・償還手数料を0円に設定することでユーザー負担を極力減らす方針を明らかにしています。これは従来、海外ステーブルコイン(USDTやUSDCなど)を入手する際に暗号資産交換業者で購入→両替というプロセスが必要で、そのたびに手数料が発生していたのに比べると、大きな利点です 。JPYCなら銀行振込で直接自分のウォレットにJPYCを入手・返金でき、その際の発行手数料はゼロなので、円をそのままデジタル円に変える感覚で利用できます。
もっとも、まったく費用がかからないわけではありません。JPYC購入時には以下の実費程度のコストが発生します。
JPYC公式販売所で円を振り込む際の振込手数料です。利用する銀行や金額によって異なりますが、例えばJPYC社指定の銀行口座(GMOあおぞらネット銀行等)を利用すれば振込手数料が無料、その他銀行でも数百円程度で済む場合があります。できるだけコストを抑えたい場合は、振込手数料無料の銀行を選ぶと良いでしょう。
JPYCを受け取ったり送金したりする際に、利用するブロックチェーン上で発生する手数料です。Ethereumネットワークではガス代が高めですが、PolygonやAstarなどでは数十円程度に抑えられます。JPYCは複数チェーン対応なので、手数料を節約したい場合はガス代の安いチェーン上でJPYCを受け取る/利用するのがおすすめです。例えばPolygon版JPYCを希望すれば比較的安価に送付してもらえます(購入時に対応チェーンを選択可能な仕組みになると予想されます)。
JPYCが取引所に上場された場合、取引所経由で売買する際にはその取引所の手数料体系が適用されます。国内取引所では販売所形式ならスプレッド(売買価格差)が実質的な手数料となり、取引所形式なら数%未満の取引手数料がかかります。例えばBybitでJPYCを取引する場合、約定ごとに0.1%前後の売買手数料が発生します(通常プランの場合)。もっとも、これらは他の仮想通貨を取引する際と同程度のコストなので特別高額ではありません。ただ頻繁に売買すると積み重なるため、長期保有目的なら公式販売所で入手してウォレットで保管、必要な時だけ交換するといったスタイルが手数料を最小化できます。
JPYCは、日本初の本格的な円建てステーブルコインとしてまもなく登場する期待のデジタル通貨です。2025年秋には購入可能となり、公式サイトを通じて1円単位で手に入れられるようになります。JPYCを活用すれば、これまで円では直接参加しづらかった暗号資産の世界に、日本円のまま飛び込むことができます。手数料面でもユーザーフレンドリーで、円からJPYC、そしてまた円への交換までスムーズに行える設計となっています。
まずは発売開始の公式アナウンスを待ちつつ、準備できることから始めましょう。国内ならコインチェックで口座開設して仮想通貨の基礎に触れておいたり、海外ならBybitのアカウントを作って取引画面に慣れておくのも良いでしょう。JPYC自体は安定した通貨ですが、その周辺のサービスを利用することで新たな投資機会や利便性を享受できます。日本円がブロックチェーン上で自在に使える時代はすぐそこまで来ています。ぜひJPYCの動向に注目し、上手に活用してみてください。







