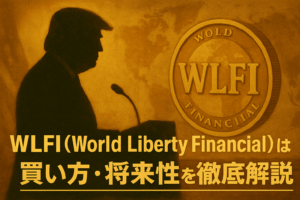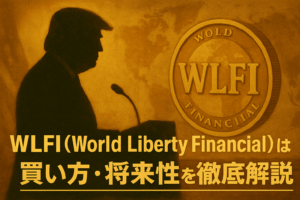キャンペーンを活用して無料で稼ぐ
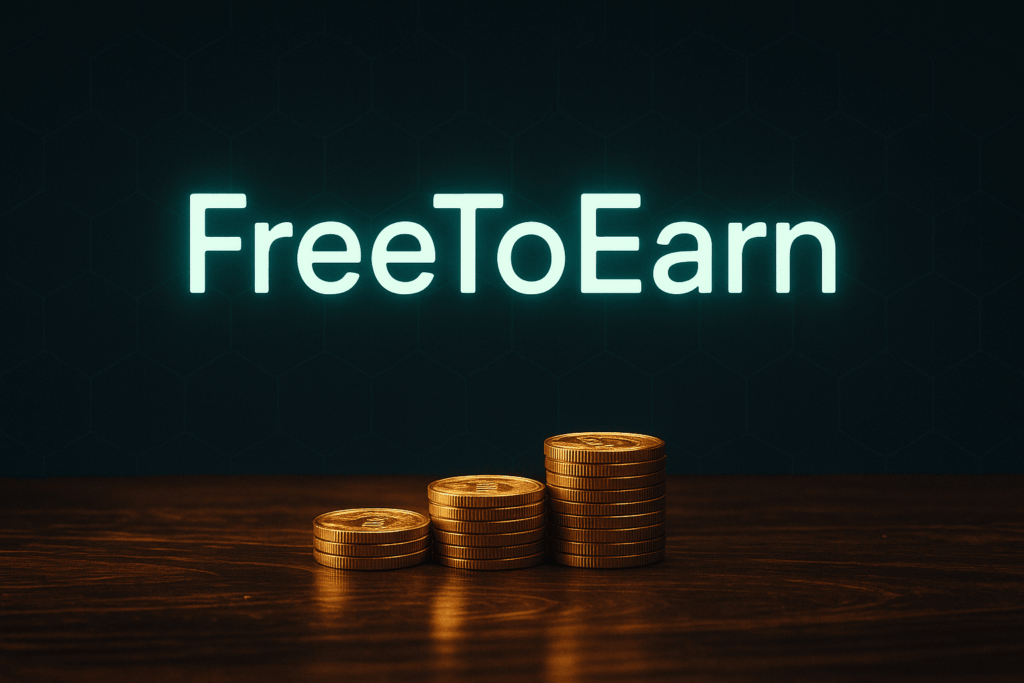
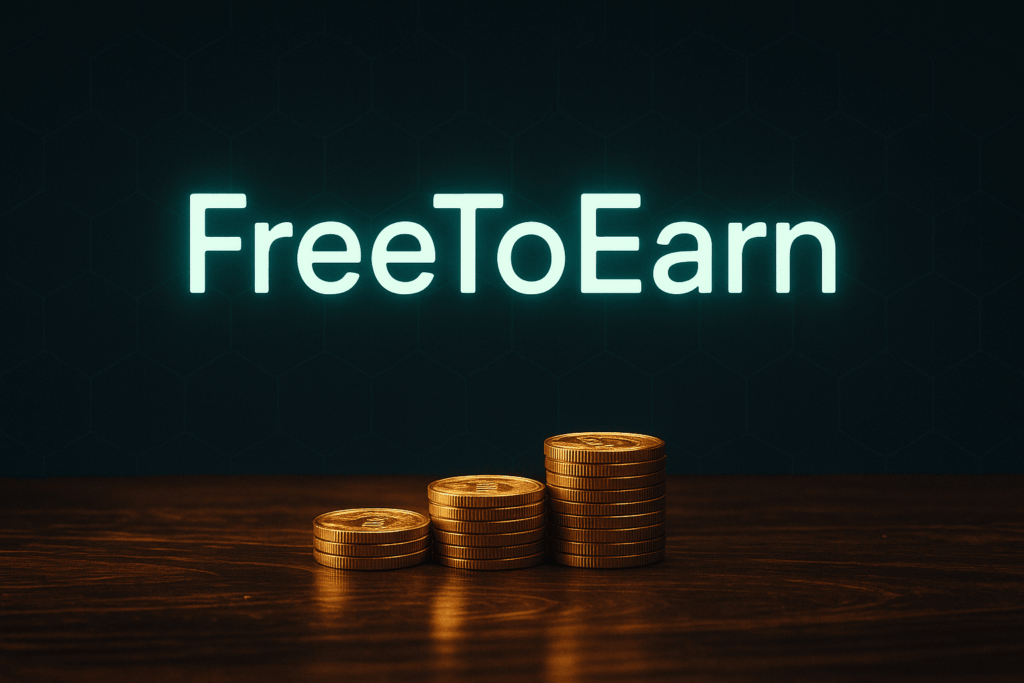

暗号資産の運用先を検討する際、年利4〜5%が自動で付与されるレイヤー2ネットワーク Blast は有力な選択肢です。
BlastにETHやステーブルコインをブリッジしてウォレットに保有しておくだけで、イーサリアムのステーキング報酬やオンチェーン米国債運用に由来する利回りが自動的に反映され、複利で資産が増加します。
本記事では、その利回りの仕組みを体系的に解説し、少額から大口までの複利シミュレーションを提示します。
増えた資金をデビットカードで即日使う実用ワザや、Bybit経由で最短ルートで運用を始める手順も網羅します。
リスクとリターンをバランス良く押さえた“ほったらかし運用”の最前線をお届けします。




Blast(ブラスト)は、NFTマーケットプレイス「Blur」の創設チームが開発したEthereumの新しいレイヤー2(L2)ブロックチェーンです。
最大の特徴は、ETHおよびステーブルコインに対するネイティブ利回りを提供する世界初のL2であることです。通常、他のL2では資産をブリッジしても何も利息は付きません。
しかしBlastでは、ブリッジして預けた資産が時間の経過とともに自動で増えていきます。実際、Blast上ではETHに約4%、USDC/USDT/DAIなどのステーブルコインに約5%の年利(APY)が付与されます 。この利率は他のL2がデフォルト0%であることを考えると非常に魅力的で、インフレによる目減りを防ぐ効果もあります 。
Blastの利回りはユーザーにとって完全に受動的な「自動収入」です。特別な運用をしなくても、資産をBlastネットワーク上のウォレットに置いておくだけで利息が得られます 。利息は資産残高に直接反映される仕組みで、ウォレット残高が徐々に増えていく形で受け取ります(=自動複利)。
たとえばBlast開発チームは「Blastウォレットに1 ETHを入れておけば、時間の経過とともに1.04、1.08、1.12 ETHに自動的に増えていく」と説明しています 。言い換えれば、年利換算で約4%のペースでETHが増えていくということです。ステーブルコインの場合も、預けたUSDCやDAIがBlast上では増えていき、年利換算約5%の利息を獲得できます。
Ethereum本体(レイヤー1)では、イーサリアム保有者がETHをステーキングすることで年数%の報酬を得ることができます。2023年のShanghaiアップグレード以降、ETHステーキングの利回りはおおむね年率4%前後で推移しています 。多くのL2ではこうしたステーキング利回りはユーザーには渡らず、L1に留まったりL2運営側の収益となっていました。そこでBlastは自前のL2上でETHをステーキング運用し、そのステーキング報酬をL2ユーザーに直接還元する仕組みを導入しました。
具体的には、BlastネットワークにブリッジされたETHは裏でLidoなどのステーキングプロトコルに預けられています。そのリワード分に相当する利息が、Blast上のユーザーETH残高に自動的に反映(リベース)される設計です 。その結果、ユーザーはBlastにETHを預けているだけでイーサリアムL1と同等のステーキング利回り(約4%)を手にできるのです。
重要なのは、ユーザー自身が別途ステーキング手続きを行う必要は一切ない点です。Blastがネットワークレベルでステーキング運用を担い、その利益をユーザーに配分してくれるため、ユーザーから見ると「ただ持っているだけ」で勝手にETHが増えていくように見えるわけです。
一方、USDCやUSDT、DAIといったステーブルコインをBlastにブリッジした場合は、ETHとは少し異なる仕組みで利回りが発生します。Blast上でステーブル資産を受け取るとき、それらはUSDBという独自のステーブルコインに自動変換されます 。USDBとは、Blastネットワーク上で発行される自動利息付与機能付きのUSD連動ステーブルコインです。USDBをウォレットに保有していると、その残高が時間とともに増えていきますが、この利息の源泉がオンチェーン国債(T-Bill)運用です 。
具体的には、BlastにブリッジされたUSDC/DAIなどの元の資金は、MakerDAOが提供するオンチェーンの米国債運用プロトコルに預けられています 。MakerDAOはドル建てステーブルコイン(DAI)の発行元であり、準備金の一部を米国債など安全資産で運用して利回りを得る仕組み(いわゆるリアルワールド資産運用)を持っています。Blastはこの仕組みを活用し、預かったステーブル資産を自動的に米国債運用に回すことで年利約5%の収益を確保し、その分をユーザーのUSDB残高に上乗せしています 。言わば**DeFi版の「預金金利」**のような形で、ユーザーは意識せずとも米国債相当の利息を享受できるのです。
なお、Blast上で増えたUSDBは、再びEthereumメインネット側にブリッジし直すときにはDAIとの交換を通じて出金されます 。つまり、将来的にBlastから資金を引き揚げる際は、増えたUSDB残高分も含めてDAI(1 DAI ≒ 1 USD)として受け取れるため安心です。利息は最終的に元本と同じく安定した形で手元に戻せるということになります。
気になるポイントとして、「そんな利回りを支払ってBlastは大丈夫なのか?」「元本が減ったりしないか?」という点があるでしょう。これについては、上記の仕組みを見れば分かる通り利回りの原資はイーサリアムのステーキング報酬および米国債の金利であり、いずれも比較的安全で持続可能なものです。
他の怪しい高利回り案件のように、新規ユーザーの資金を原資とするポンジスキームではありません。また、Blast自体は大手VCのParadigmやStandard Cryptoから資金調達済みであり 、Blurで実績のある開発チームが運営しています。もっとも、スマートコントラクトやブリッジのリスクはゼロではないため、利用する際は公式情報のアップデート確認や、無理のない範囲の資金運用を心がけることも大切です。
実際にBlastの利回りで資産がどの程度増えていくのか、複利運用による残高の推移をシミュレーションしてみましょう。ここでは計算を簡略化するため、年利4%(ETHの場合)と5%(ステーブルコインの場合)が期間中ずっと一定と仮定し、元本が時間とともに増加する様子をモデル化します。利息は自動的に元本に組み込まれていく(自動複利)ため、時間が経つほど利息額も雪だるま式に増えていきます。
下の表では、初期元本を「100」とした場合に経過年数ごとに残高がいくらになるかを比較しています(100は任意の単位:例えば100万円でも100 ETHでも考え方は同じです)。左が年利4%(ETH相当)、右が年利5%(ステーブルコイン相当)のケースです。
| 経過年数 | 元本100の将来価値(年利4%) | 元本100の将来価値(年利5%) |
|---|---|---|
| 0年 | 100 | 100 |
| 1年 | 104 | 105 |
| 3年 | 112.5 | 115.8 |
| 5年 | 121.7 | 127.6 |
| 10年 | 148.0 | 162.9 |
ご覧のように、年利4%と5%では長期ではそれなりの差が生まれます。どちらにせよ、預けた資産が10年で約1.5~1.6倍になる計算です。これは日本の銀行預金(金利0.001%台)では到底期待できない増え方ですし、仮にご自身でイーサリアムをステーキング運用しようとすると手間やロック期間が発生しますから、何もしなくてもこれだけ増えるのは画期的と言えます。
もちろん暗号資産の世界で10年先を読むのは難しいですが、短期間でも「塵も積もれば山」となるのが複利運用の魅力です。例えば年利5%なら、1ヶ月あたり約0.4%の利息がつくイメージなので、100万円なら月4,000円ほど、1,000万円なら月4万円ほどが自動で増える計算です。わずかと感じるか大きいと感じるかは人それぞれですが、少なくとも遊ばせておくより確実に有利なのは間違いありません。
「お小遣い稼ぎ」程度の感覚でも、Blastなら銀行預金より遥かに高利なので預ける意義はあります。例えば10万円のステーブルコインを預ければ年間約5,000円の利息がつく計算です。5,000円あれば美味しいランチ数回分にはなりますし、ほぼノーリスク(価格変動のないステーブル)の運用先としては悪くありません。何より手間がかからず自由に出し入れ可能なので、気軽に試せるのも魅力です。
例えば500万円相当をBlastで運用すると、年間利息はだいたいETHなら20万円、ステーブルなら25万円ほどになります。銀行に預けていては数百円程度にしかならない額が、Blastならちょっとした副収入規模になります。月々に直せば約2万円前後が自動で入るイメージで、これは光熱費やスマホ代の支払いに充てられるくらいのインパクトがあります。余裕資金をお持ちであれば、積極的に活用したいゾーンでしょう。
富裕層や機関投資家にとっても、Blastの利回りは無視できない収益源となりえます。1億円を年利5%で運用すれば年間500万円ですから、人件費一人分に相当するリターンです。従来、このクラスの資金を安全に運用しようとすれば国債や社債購入という選択でしたが、暗号資産の世界でも同程度の低リスク利回りを得られるようになった点で画期的です。ただし、大口の場合は分散投資の観点からセキュリティリスクにも注意が必要ですので、Blastに預けるのは資産の一部に留める、マルチシグウォレットを使う等の慎重さは持っておきましょう。
まずは運用したい資産(ETHやUSDCなどのステーブルコイン)を用意します。既にお持ちの方はそれを使えますし、持っていなければ国内外の主要取引所(例:Coincheckやビットバンクなど)で購入してください。購入後、ご自身のウォレット(MetaMask等)に資産を移しておきます。


ブラウザでBlast公式サイトのブリッジページにアクセスし、ウォレットを接続します。ブリッジ画面でEthereumからBlastへの資産移動を指定し、先ほど用意したETHやステーブルコインを送ります。ガス代(手数料)が発生しますが、必要な手数料を確認してトランザクションを実行してください。※ステーブルコインを送る場合、Blast側で自動的にUSDBに変換されます 。
ブリッジ処理が完了すると、資産がL2のBlastネットワーク上に反映されます。あとはそのままウォレットに資産を保持しているだけでOKです。先述の通り、利息はブロックごと(ほぼリアルタイム)に発生し、少しずつ残高に反映されていきます 。特別なステーキング契約に預けたり利息受取手続きをしたりする必要はありません。時間の経過とともに、確実に資産が増えていくのを見守りましょう。
一定期間運用したら、増えた分も含めて資産を使いたくなるでしょう。その場合は2と逆の操作でBlastからEthereumへブリッジし直すことで出金できます(出金解禁は2024年2月に実装済み)。ETHはそのまま、USDBはDAIに交換されて戻ってきます 。出金後、取引所に送れば日本円など法定通貨に換金可能です。また、利息分だけを残して元本を引き出すなど柔軟な運用もできます。
さらに、せっかくステーブルコインで利息を得たなら、暗号資産デビットカードを使って直接日常生活で使う手もあります。例えばKASTカードはUSDCやUSDTなど主要ステーブルコインをチャージしてVisa/Mastercard加盟店で支払いに使えるサービスです。
Blastで増やしたUSDCをKASTに送金すれば、そのままコンビニやネット通販で利用でき、利息で得た分を実生活の買い物に充当できます。KASTは発行手数料無料で利用でき、2025年は最大4%のキャッシュバックも提供されているなどお得なカードです。こうしたサービスを併用すれば、Blastの利回りを「使えるお金」として引き出すハードルが一段と下がるでしょう。


Blastが実現した**「資産を持っているだけで増えていく」**仕組みは、暗号資産の新しいトレンドとして大きな注目を集めています。イーサリアムの利回りや米国債利回りといった堅実な収益源を取り込み、ユーザーに還元することで、リスクを抑えつつインフレに負けない資産運用を可能にしました 。初心者から上級者まで、手間なく恩恵を受けられる点は魅力的です。
一方で、冒頭でも述べたように利用にあたってはスマートコントラクトリスクなど基本的な注意点も忘れないようにしましょう。元本保証の銀行預金とは異なり、ブロックチェーン上のサービスである以上、技術的リスクはゼロではありません。信頼できる公式情報をチェックしつつ、余裕資金で運用を行うことが大切です。
総じて、Blastは**「堅実な利回りを手軽に得たい」**というニーズに応える画期的なソリューションです。ぜひ少額から試して、その複利効果を実感してみてください。眠っていたあなたの暗号資産が、気づけば増えている──そんな新時代の運用体験が待っています。