キャンペーンを活用して無料で稼ぐ
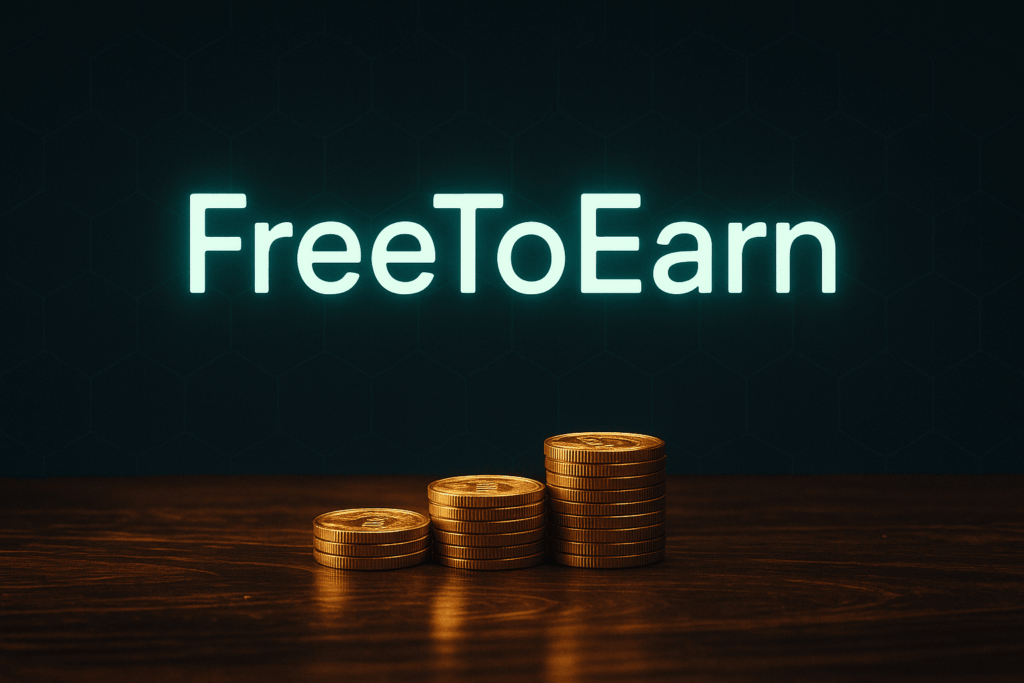
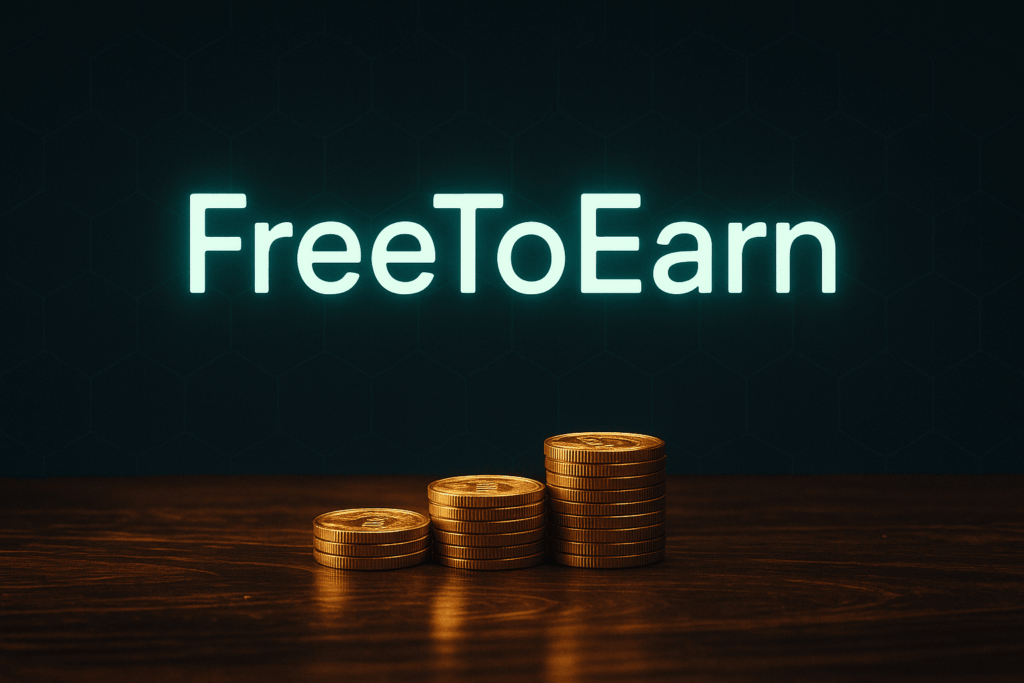

暗号資産を日常の買い物に活用できる時代が、いよいよ現実味を帯びてきました。
今年ローンチ予定の「Slash Card(スラッシュカード)」は、日本初の暗号資産対応クレジットカードとして注目を集めています。
米ドル連動型ステーブルコインUSDCを担保とした後払い(BNPL)サービスであり、Web3の資産をリアルの決済に橋渡しする革新的な試みです。
本記事では、Slash Cardの特徴やメリット、利用方法や注意点まで暫定情報を網羅的に解説します。
新しい金融サービスの全貌を一緒に見ていきましょう。
ローンチ前のため、暫定の情報をもとにまとめています。
確定情報が分かり次第、随時更新予定!


Slash Card(スラッシュカード)は、2025年に登場予定の日本初の暗号資産対応クレジットカードです 。最大の特徴は、暗号資産(仮想通貨)でクレジットカードの後払い決済ができる点にあります。従来、暗号資産を日常の買い物に使うにはいったん日本円など法定通貨に換金する手間がありました。しかしSlash Cardは、価値が安定した米ドル連動のステーブルコインUSDCを担保とすることで、その煩雑なプロセスを解消しようとしています 。ユーザーは自分の保有するUSDCを使って後払い形式で支払いを行い、後日そのUSDCで精算する仕組みです。
さらにSlash Cardは、単なる決済手段にとどまらず**「セルフカストディ型ウォレットベースの革新的金融サービス」**として位置づけられています 。セルフカストディとは、ユーザー自身が暗号資産の秘密鍵を管理する方式のことです。すなわちSlash Cardでは、ユーザーが自ら管理するウォレットとカードを連携させ、自分の資産を自分で守りながらカード決済に利用できるよう設計されています 。このアプローチによって、暗号資産の持つ分散型金融(DeFi)的なメリットと、従来のカード決済の利便性を両立させているのです。
また、Slash Cardは発行体制にも信頼性があります。大手信販会社のオリエントコーポレーション(オリコ)が国際ブランドのBINスポンサーとして提携しており、カードのネットワークはVisa加盟店で利用可能です 。発行業務は決済代行事業者の株式会社アイキタスが担当し、Slash(SLASH VISION社)は企画・開発およびブランド提供を行っています 。こうした協業により、堅牢なAML(マネーロンダリング対策)や日本の法規制遵守も徹底されており、安全性と透明性を両立したサービスとなる予定です 。実際、金融庁の資金決済法改正によりステーブルコインは電子決済手段として位置づけられ始めており、法定通貨への円滑な交換を実現するこのようなサービスが求められていました 。Slash Cardはそのニーズに応える日本初の暗号資産クレジットカードとして大きな期待を集めています。


Slash Cardでは実物の「物理カード」と即時発行できる「バーチャルカード」の2種類から選択可能です 。上図は公式サイトのカード紹介イメージで、左が物理カード、右がバーチャルカードのデザインです。
Slash Cardは利用シーンに合わせて物理カード(プラスチックカード)とバーチャルカードの二つのオプションを用意しています 。物理カードは実際のカードが自宅に郵送されるもので、日本全国への配送に対応しており、手元に届いたカードを使って街のお店で支払いができます。Visaブランドのクレジットカードとして海外の加盟店でも利用可能なので、旅行や出張先でも活用できるでしょう 。さらに、追加で複数枚発行することも可能なため、家族カード的な使い方や用途別のカード分けも想定されています 。
一方のバーチャルカードは、オンライン決済に特化したデジタルなカードです 。申し込み後に即座に発行され、スマートフォンやPC上でカード番号を確認してネットショッピングなどに利用できます。バーチャルカードも複数発行が可能で、用途ごとにカードを使い分けることができます 。また今後、Apple PayやGoogle Payといった各種モバイル決済への対応も予定されており、スマホのウォレットアプリにバーチャルカードを取り込んで店舗でタッチ決済する、といった使い方も視野に入っています 。実物のカードが不要で手軽に発行できる点は、デジタルネイティブなユーザーやすぐにサービスを試したい方にとって大きな利点でしょう。
Slash Cardは複数のブロックチェーンネットワークに対応しており、Solana・Ethereumなど主要チェーンのトークンでチャージ可能です 。上図はサポートされるチェーンの例で、今後さらに対応ネットワークが拡充予定とされています。
暗号資産には様々なブロックチェーン(ネットワーク)が存在しますが、Slash Cardはマルチチェーン対応によって高い互換性を実現しています 。現時点で公表されている対応ネットワークはSolana、Ethereum、Binance Smart Chain、Polygon、Avalanche、Mantleなど主要なチェーンが名を連ねています 。この他にも**“and More…”**と記載されており、順次サポートチェーンを拡大予定と発表されています 。つまり、ユーザーはこれら複数のブロックチェーン上の資産を利用してSlash Cardにチャージできる可能性があるということです。
実際の利用シナリオとしては、例えばSolanaネットワーク上のUSDCやEthereum上のUSDCなど、異なるチェーン上のUSDCでもカード残高にチャージ可能になると考えられます。あるいは、将来的に対応が進めば各チェーン上の主要トークン(BTCやETH等)を直接担保として使えるようになる可能性もあるでしょう(※現時点では発行元がUSDCを担保とすると明言していますが、他トークンからUSDCへの交換チャージができる仕組みが提供されるようです )。いずれにせよマルチチェーン対応のおかげで、特定のブロックチェーンに資産を持っているユーザーでも柔軟にサービスを利用できる点は大きなメリットです。自分の使っているチェーンが限定されていても、Slash Cardが橋渡ししてくれることで暗号資産の利用範囲が格段に広がるでしょう。
Slash Card最大の特徴の一つが、セルフカストディ(自己管理)ウォレットとの連携です。ユーザーは自身の暗号資産ウォレット(いわゆるアンホステッドウォレット)をSlash Cardアプリに接続し、そのウォレット内のトークンから直接カード残高へチャージできます 。例えば、お手持ちのMetamaskやPhantomといったウォレットを紐づけて、そこに保管しているUSDCをカードにチャージするといった具合です。これにより暗号資産を自分で管理したままカード払いに利用できるため、取引所や第三者に資産を預ける必要がなく、安全面でも安心感があります 。自分のウォレットから必要な時に必要な分だけチャージできるので、資産のコントロールが手元に残る点は、クリプトユーザーにとって重要なポイントでしょう。
では、暗号資産ウォレットを持っていない初心者の場合はどうでしょうか。その点も心配ありません。Slash Cardではメールアドレスだけで簡単にアカウントを作成可能で、アプリ内で自動生成されるウォレット機能を使ってカードにチャージすることもできます 。専門的な知識がなくても、まずはアプリ上でウォレットを発行し、そこに日本円で購入した暗号資産(将来的には国内取引所で入手可能なUSDCなど)を送ってチャージする、といった利用方法が想定されています。現在、日本の大手取引所でUSDCの取り扱いが始まろうとしており 、今後は暗号資産初心者でもスムーズにUSDCを入手・チャージできる環境が整っていくでしょう。
なお、カードの利用限度額について公式発表はまだありませんが、一般的な後払いサービスと同様に、ユーザーがチャージ(または担保提供)したUSDCの範囲内で利用額が決まるものと思われます。これはユーザー自身があらかじめ用意した暗号資産以上に勝手に借金が膨らむ心配がないことを意味し、安全な範囲で後払いの利便性を享受できる仕組みです。カード残高はUSDC建てで管理されており、チャージ元のトークンが異なる場合でも都度USDCに換算されます 。裏を返せば、利用時にはUSDC⇔円の為替レート変動や暗号資産の価格変動リスクを意識する必要がありますが、ステーブルコインであるUSDCを用いることでそのリスクを極力小さく抑えています。これらの工夫によって、「便利だけれどリスクが高い」というこれまでの暗号資産決済の弱点を克服し、安心して日常利用できる決済サービスを目指しているのがSlash Cardと言えるでしょう。
利用者にとって嬉しいリワードプログラムもSlash Cardの大きな魅力です。他のクレジットカードにもポイント還元等はありますが、Slash Cardでは独自トークンでリワードが還元される点で従来とは一線を画します 。大きく分けて「紹介リワード」と「会員ランク特典」の2種類が用意されています。
紹介リワードは、Slash Cardを友人や知人に紹介することで得られる特典です。具体的には、自分が紹介したユーザーがSlash Cardを利用した金額に応じて、紹介者に一定のトークンが還元される仕組みになっています 。通常のクレジットカードであれば紹介特典は現金やポイントだったりしますが、Slash Cardではポイントではなく暗号資産トークンで受け取れる点が特徴です 。トークンで報酬をもらえることで、そのトークンをさらにカード支払いに使ったり、別の好きな暗号資産に交換したりと自由度の高い活用が可能になります 。言わば“使って稼ぐ (Pay-to-Earn)”仕組みとも言え、カード利用そのものが新たな暗号資産獲得の機会につながるわけです。
次に会員ランク制度ですが、こちらはSlashエコシステム内での貢献度に応じてユーザーにランクが付与され、ランクに応じた特典を受けられるプログラムです 。例えば、Slashの提供する他のサービス(決済プラットフォーム等)も利用していたり、一定額以上カード決済を続けたりするとランクアップし、ランクごとの特典(手数料割引や限定キャンペーン参加等)が受け取れる可能性があります 。このようにユーザーのロイヤリティ向上を図る仕組みは、継続的な利用促進にもつながります。カードを長く使えば使うほどメリットが増すため、ユーザーとしても積極的に活用しやすくなるでしょう。
さらに公式情報によれば、上述の紹介・ランク以外にも様々なリワードやプログラムを準備中とのことです 。エアドロップ(特定条件を満たしたユーザーへのトークン無料配布)や提携プロジェクトからの特典提供など、Slash Cardを通じて国内外の暗号資産プロジェクトとユーザーを繋ぐユニークな施策も計画されているようです 。単に決済手段を提供するだけでなく、利用者が暗号資産コミュニティの一員として楽しめるような仕掛けが盛り込まれている点は、Slash Cardならではの魅力と言えます。
現在、Slash Cardはクローズドβ版への事前登録を受付中です 。まず公式サイトからメールアドレスを登録し、案内に従ってユーザーアカウントを作成します。アカウント登録時には氏名やメール確認など基本情報の入力が必要です(メールだけで登録可能で、その後必要に応じウォレットを接続する形になります )。
アカウント開設後、サービスを利用するには**本人確認手続き(KYC)**が必須となります 。運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類を提示し、18歳以上の日本在住者であることを確認するプロセスです 。このステップは、金融サービスとしての法令遵守と不正防止のために欠かせません。
KYCが承認されたら、カードの種類を選んで発行手続きに進みます 。物理カードを選んだ場合は発送先住所の登録等が必要になり、バーチャルカードならオンライン上ですぐカード番号等が発行されます。公式情報によれば、アカウント登録~カード発行までは比較的シンプルな流れとのことです 。物理カードの場合、数日~1週間程度で郵送されて手元に届くイメージでしょう。
カードを利用する前に、カード残高にUSDCをチャージする必要があります 。チャージ方法は二通りあり、自分の保有ウォレットから指定アドレスへUSDCを送金するか、アプリ内ウォレットに入金した日本円等でUSDCを購入・充当する形になると考えられます。いずれの場合もカード残高がUSDCで補填されて初めて決済に使用可能となります 。チャージ額=利用限度額となるため、使う予定に合わせて適宜チャージしておくと良いでしょう。
準備が整ったら、あとは通常のクレジットカードと同様に決済に利用できます。実店舗では物理カードを提示して支払い(またはバーチャルカードをスマホのウォレットアプリに登録してタッチ決済)、オンラインではカード番号情報を入力して決済します。Visaカードとして処理されるため、対応店舗の広さは言うまでもなく非常に幅広いです 。利用額はリアルタイムまたは一定周期でUSDC残高から差し引かれ、残高が不足すると新たなチャージが必要になります。
現時点の情報では、アカウント開設費は無料と案内されています 。ただしカード発行時に別途費用が発生する見込みです 。物理カードの場合、発行手数料や配送費用等がかかる可能性があります。一方バーチャルカードは基本的に無料で発行できるケースもありますが、正式リリース時の料金体系を確認しましょう。年会費については未発表ですが、仮に有料でもリワード特典で十分元が取れる設定にする可能性があります。いずれにせよ公式からの料金発表に注目してください。
国内利用の場合、円建て決済となりUSDCから円への換算が発生します。その際の手数料やレートはサービス提供側が定めるレートが適用されるはずです。海外利用時は通常のクレジットカード同様に為替レートで円換算されますが、USDC自体がドルと等価なのでドル→円のレートがそのまま適用される形になるでしょう。海外事務手数料などが別途かかるかは現在不明ですが、従来のカードと同程度(1.63%前後)の可能性があります。手数料体系も正式リリース時に確認が必要です。
前述のとおり、Slash Cardを利用できるのは満18歳以上の日本在住者に限られます 。学生でも18歳以上であれば利用可能と思われますが、未成年や日本国外居住者は対象外です。また、利用開始には厳格な本人確認が求められ、不正利用防止のために審査が行われます。暗号資産を扱うサービスということで、登録内容とKYC情報が一致しない場合や、不審な取引が検知された場合はサービス利用が停止される可能性もあります。健全なサービス運営のために必要な措置ですので、正確な情報提供を心がけましょう。
Slash Cardを利用して暗号資産で支払いを行うことは、税務上「暗号資産の処分(売却)による課税対象取引」とみなされる場合があります。とりわけUSDCなどのステーブルコインであっても取得時と使用時で円換算額に差異が生じれば利益(または損失)に対して課税される可能性があります。公式でも「税金計算は本サービスには含まれておらず、利用者自身で対応する必要がある」旨が明記されています 。つまり、Slash Cardの利用によって生じる暗号資産の譲渡損益は、自分で記録・計算し確定申告等を行う必要があります。現状では暗号資産決済時の自動税金計算機能などは提供されていないため、この点はユーザー側でしっかり管理しましょう。


最大のメリットは何と言っても、暗号資産を簡単に日常の支払いに使えるようになる点です。これまでビットコインやイーサリアムなど暗号資産は「値上がり益を狙う投資対象」あるいは「投機的な資産」と見られがちで、実際の買い物で使う機会は限られていました。しかしSlash Cardの登場によって、暗号資産が日々の決済手段として本格的に活用される道筋が日本でも開かれる可能性があります 。例えば、手持ちのUSDCがあればコンビニやネット通販でそのまま支払いに充てられ、銀行口座から日本円を引き出すのと同じ感覚で資産を使えるわけです。暗号資産が**実用的な「お金」**として機能し始めるインパクトは大きく、ユーザーにとって資産活用の幅が一気に広がるでしょう。
また、海外旅行やオンラインサービス利用時の通貨問題解消というメリットもあります。米ドルにペッグされたUSDCを使うSlash Cardなら、海外のVisa加盟店でそのまま使っても為替手数料の面で有利に働く可能性があります(円→ドル両替よりスプレッドが小さいなど)。あるいは、日本未対応の海外オンラインサービスでもクレジットカード決済さえできれば暗号資産資金で利用可能になるため、グローバルな購買活動がしやすくなります。暗号資産を持っているだけでは享受できなかった利便性が、Slash Cardによって一気に身近になる点は見逃せません。
セルフカストディ型という特徴から生まれる安全性と主体性も重要なメリットです。ユーザー自身が資産管理をする前提のサービスであるため、「サービス提供元がハッキングされて預けたコインが流出」といった心配が比較的少なくなります。もちろんカード利用時には必要分のUSDCを預ける形になりますが、自分のウォレットから都度チャージする形式であれば大金を常時預けっぱなしにしなくて良いのは安心材料です。自分でセキュリティに気を配りながら利用できるため、リテラシーの高いユーザーほど恩恵を感じられるでしょう。
さらに、オリコやアイキタスといった既存の金融事業者が関与することで、万一のトラブル時の対応やサポート体制にも信頼感があります。従来の暗号資産サービスは「自己責任」が強調されすぎる傾向もありましたが、Slash Cardはその点でWeb2的なきめ細かいユーザーサポートも期待できます。技術的革新と既存金融のノウハウ融合により、安全かつ使いやすいサービスとなっている点はユーザーにとって大きなメリットです。
Slash Cardの試みは、ユーザー個人の利便性向上だけでなく、暗号資産市場全体の活性化にもつながる可能性があります。実際、発行元のSlash社は「日本の暗号資産市場のさらなる発展をめざす」と述べており 、ステーブルコイン決済が浸透する市場環境を整備することで業界全体を押し上げる意図が伺えます。多くの人が暗号資産を実生活で使う=実需が生まれることになれば、暗号資産の価値安定性や信用力も増し、ひいては暗号資産価格の健全な成長にも寄与するでしょう。
また、Slash Cardのリワードプログラムを通じて国内外のプロジェクトとユーザーが交わる機会が創出される点も見逃せません。紹介プログラムやランク特典、Pay-to-Earn的な施策によって、日本のユーザーが新しいトークンやプロジェクトに自然と触れる機会が増えていきます。これは暗号資産コミュニティの拡大・接続に他なりません。日本はこれまで規制上の理由もあり暗号資産のユースケース創出で後れを取っていましたが、Slash Cardがきっかけとなって**「使って増やす」エコシステム**が国内にも根付けば、海外に劣らない活発なコミュニティ形成が期待できます。
総じて、Slash Cardは暗号資産を取り巻く様々な壁を取り払い、新たな価値循環を生み出すポテンシャルを秘めています。もちろんサービスが定着するには時間も検証も必要ですが、その第一歩が既に踏み出されたという事実は、業界にとって明るいニュースと言えるでしょう。
最後に、Slash Cardが切り拓く今後の展望について触れておきます。前述の通り、このカードの登場は日本における暗号資産決済の重要なマイルストーンとなる可能性があります 。もしSlash Cardが広く受け入れられ、成功を収めれば、他の企業や銀行も追随して類似サービスを展開するかもしれません。そうなればユーザーは選択肢が増え、暗号資産で支払いできる機会がさらに拡大するでしょう。まさに**キャッシュレス革命の次なる一手が「クリプト決済」**という未来が現実味を帯びてきます。
また、Slash Card発行元のSLASH VISION社自体、暗号資産決済プラットフォーム「Slash Payment」を提供してきた背景があります 。そのノウハウやサービス群とカード事業が統合されていけば、ECサイトや店舗への暗号資産決済導入が一層容易になるかもしれません。つまり、カード利用者だけでなく加盟店側にも波及効果が期待できます。ポイントカードならぬトークン還元カードが普及すれば、小売店やオンラインサービス側も暗号資産を活用したマーケティングを展開でき、新たな経済圏が形成される可能性もあります。
Slash Cardはまだローンチ前とはいえ、すでに多くの関心が寄せられており、事前登録も盛況のようです。公式発表では「2025年前半の発行を目標」とされていましたが 、7月現在でクローズドβが開始されたことから、正式サービス開始は目前と言えます。私たちユーザーは、その動向を注視しつつ、自身がこの新しい波にどう乗るかを考えてみても良いでしょう。暗号資産の未来が今、手元のカードとなって現れようとしている──Slash Cardがもたらす新時代に期待が高まります。